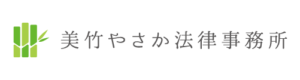【判示事項】
婚姻意思とは「社会通念上夫婦とみられる関係を形成しようとする意思」を指すと解されるところ、当該関係の形成は、同居、協力義務、相続といった婚姻に基本的な効果を当然に伴うものであるから、婚姻のための意思能力があるというためには、これらの基本的な効果を理解する程度の能力は必要といえるが、その法定効果まで理解する能力を要するものではないとして、妻である被告・被控訴人に本件婚姻時に婚姻のための意思能力がなかったとは認め難いとした事例
事件名 婚姻無効確認請求(控訴)事件
原審東京家裁 請求棄却 令2・11・20 判決
控訴審東京高裁 令2(ネ)4454号
控訴棄却 令3・4・27 民4部判決
上告・上告受理申立て 上局棄却・不受理確定
出典 家庭の法と裁判 №.55/2025.4 p44
【事案の概要】
関係者
原告・控訴人 X 夫A(成年被後見人)の弟 推定相続人
被告・被控訴人 Y1 夫Aの成年後見人
同 Y2 妻
X(原告・控訴人)は、婚姻時には、夫であるAには、若年性認知症により婚姻による形成される社会的な意味や財産関係も含めた意味、死後の相続などの問題等の意味内容を理解する能力がなく、したがって婚姻意思が認められなかったとして、妻Y2及び夫Aの成年後見人Y1の両名を被告として、婚姻無効確認請求訴訟を提起した。
これに対してY1,Y2(被告・被控訴人ら)は、Aには、婚姻の意義を理解しかつ判断できる能力を有していたから婚姻意思はあったと主張した。
原審東京家裁は、Aは婚姻時、若年性認知機能障害が見られたとは言え、その言動や交際状況を総合考慮したうえで、婚姻意思が認められなかったとは認め難いとして、X原告の請求を棄却し、X原告はY1,Y2被告両名を被控訴人として控訴を提起したが、本件控訴審も、原審と同様の理由により、X控訴人の控訴を棄却した。
【控訴審判決理由の骨子】
婚姻意思とは「社会通念上夫婦とみられる関係を形成しようとする意思」を指すと解されるところ、当該関係の形成は、同居、協力義務、相続といった婚姻に基本的な効果を当然に伴うものであるから、婚姻のための意思能力があるというためには、これらの基本的な効果を理解する程度の能力は必要といえるが、その法定効果まで理解する能力を要するものではないとして、夫Aに本件婚姻時に婚姻のための意思能力がなかったとは認め難いとして請求を棄却した原審判決を維持し、控訴を棄却した。
【若干のコメント】
1 指導的な最高裁判決は、民法742条1号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があつたとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じないと解している(最高裁第二小法廷昭和44年10月31日判決民集23巻10号1894頁)。
2 学説としては、この意思について、形式説(婚姻の届出をする意思のみで足りる)、実質説(届出意思のみでは足りず、社会通念上夫婦と認められる関係を形成しようとする意思が必要)の対立がある。
もっとも、実質説は「社会通念」という一定の理念型に沿った夫婦を基準に「夫婦であると認められる関係の設定を形成しようとする意思」の有無を判断するものであり、家族関係が多様化複雑化した現代社会において判断基準として有効に機能しうるかという問題があり、学説上は種々の説に分かれている。
3 本判決は、「社会通念上夫婦とみられる関係の形成は、同居、協力義務、相続といった婚姻に基本的な効果を当然に伴うものであるから、婚姻のための意思能力があるというためには、これらの基本的な効果を理解する程度の能力は必要といえるが、その法定効果まで理解する能力を要するものではない」とのどちらかと言えば緩い実質説に立ったうえでの判断であると考えられる。
4 なお、本件訴訟は、身分関係の当事者(夫婦)以外の者が原告となっているので、人訴法12条2項により身分関係の当事者である夫婦双方が被告となり、この2人に対する請求の関係は固有必要的共同訴訟と解されるので訴訟物は1個である。
また、被告とされる2人のうちの1人が成年被後見人であるので人訴法14条1項本文により、その成年後見人が法定訴訟担当として成年被後見人のために被告となっている。
控訴審判決は、原審東京家裁判決を大幅に引用処理しているので読みずらいが、本判決及び原審判決掲載雑誌である判例時報2563号5頁以下は、引用部分を具体的に註記しているので、参照していただきたい。