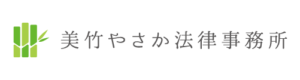離婚訴訟に附帯する財産分与の申立てにおいて、いわゆるオーバーローン不動産がある場合の財産分与について判断した事例
【東京高裁令和6年8月21日判決 家庭の法と裁判55巻60頁】
【事案の概要】控訴人(原審本訴被告・反訴原告)Y、被控訴人(原審本訴原告・反訴被告)X
- 原審で、Xは本訴で離婚と慰謝料請求、Yは反訴で離婚と慰謝料請求、財産分与および年金分割の申立て
- XとYは婚姻後にX名義で不動産(以下「本件自宅」)を購入、その後Yが本件自宅から出る形で別居開始
- 別居開始時点で、本件自宅は、評価額を住宅ローン債務が上回る、いわゆるオーバーローン不動産
- 本件自宅と住宅ローン債務を含めて、積極財産の総額から消極財産の総額を引くと、マイナスになってしまう事案
【争点】財産分与について
いわゆるオーバーローン不動産がある場合の財産分与の算定方法について、不動産と住宅ローン債務をともに財産分与の対象から除外した上で、残余の積極財産を分与の対象とするか(Yの主張、算定方法①)、それとも、不動産と住宅ローン債務を含めた夫婦それぞれの積極財産の総額から消極財産の総額を控除した残額を対象とする(算定方法②)か。
【原審:横浜家裁横須賀支部令和5年12月26日判決】
算定方法②によるとし、Yの申立てを却下
【高裁の判断】
控訴棄却
財産分与については、原則として算定方法②によることとし、「ただし、住宅用不動産は、他の財産分与の対象となる財産(動産、流動資産)とは性質を異にし、住宅ローン債務は当該不動産を取得することを目的とする借入債務であって、離婚の成立後の支払分は財産分与により当該不動産の全部を取得する配偶者にとってその取得のための対価的性質を持つ側面もあるといえるから、上記のような清算方法によったのでは財産分与における当事者間の衡平を害するというべき事情が認められる場合には、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当該事情を民法768条3項の『一切の事情』として考慮して、上記清算方法と異なる財産分与の額および方法を定めることにも合理性が認められる」とした。
そして、「衡平を害する場合」として、オーバーローン不動産があり、他の財産と通算する算定方法②によっては不動産を取得できない配偶者が、当該不動産から退去を余儀なくされる上、分与される財産が存在しないか極めて少額である一方、他方の配偶者は所有名義人として当該不動産の使用収益を継続しつつ離婚後の収入および取得財産によって住宅ローンを返済することで最終的に負担のない同不動産の所有権を取得し、あるいはこれを処分することで一定の利益を得る相当程度の蓋然性が認められるときを挙げ、本件についてはこのような財産分与における当事者間の衡平を害するというべき事情は認められないとした。