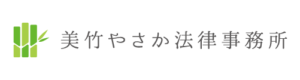他の男性の嫡出子を胎児認知した者による認知無効確認請求が権利濫用に当たるとされた事例
[東京家判2023年(令和5年)3月23日判決 家庭の法と裁判55号90頁]
【当事者】
X 原告、日本国籍を有する男性
Y 被告、2006年(平成18年)生まれ
A Yの母、ベトナム国籍を有する女性
B Aの元夫、ベトナム国籍を有する男性
C Xの元妻
【事実経過】
|
1993年(平成5年)11月11日 |
X、Cと婚姻(H7長女D、H9長男E出生) |
|
2002年(平成14年)4月4日 |
A、日本に滞在開始 |
|
2003年(平成15年)2月11日 |
AとB、qにおいて婚姻の登録 |
|
2003年(平成15年)頃 |
AとB、sの住居において同居開始 |
|
2003年(平成15年)4月頃 |
X、Cと別居 |
|
2005年(平成17年)6月頃 |
Aがtの住居に転出して別居開始 |
|
2005年(平成17年)10月頃 |
AとX、交際開始 |
|
2005年(平成17年)12月頃 |
AとX、同居開始 |
|
2006年(平成18年)頃 |
A、Yを懐胎している旨の診断 |
|
2006年(平成18年)7月20日 |
AとB、q人民裁判所において合意による離婚の承認(本件離婚承認) |
|
2006年(平成18年)頃 |
X、p長に対し、Yに係る胎児認知(本件胎児認知)の届出、受理 |
|
2006年(平成18年)頃 |
A、Yを出産。戸籍上、YはXとAの長女、日本国籍を有するものとされている |
|
2020年(令和2年)6月頃 |
A、X以外の男性との交際を開始 |
|
2020年(令和2年)8月頃 |
A、YとともにXと別居 |
|
2020年(令和2年)10月14日 |
X、Cと離婚の届出 |
|
2020年(令和2年)11月25日 |
A、Xに対して養育費分担調停 |
|
2021年(令和3年)5月20日 |
X、Yに対して認知無効確認調停 |
|
2021年(令和3年)7月28日 |
X、Yに対して認知無効確認訴訟 |
【争点】
⑴ 本件胎児認知が有効か(YはBの嫡出子か)
⑵ Xの認知無効確認請求が権利濫用に当たるか
【裁判所の判断】
⑴ 本件胎児認知が有効か(肯定)
「まず、・・・YはAがBとの婚姻期間中に懐胎した子であると認められる。そして・・・法の適用に関する通則法28条1項は、夫婦の一方の本国法で子の出生の当時におけるものにより子が嫡出となるべきときは、その子は、嫡出である子とする旨を定めているところ、ベトナム婚姻家族法63条1項前段は、婚姻期間中に妻によって分娩又は懐胎された子は、夫婦の共通の子とする旨を定めているから、YはBの嫡出子であるというべきである。」
「日本の民法下では、認知は、その性格上、現に父がある子を対象としてはすることができないと解されているから、YがBの子であるとされる限りは、本件胎児認知を有効なものと認めることはできないというべきである。」
⑵ Xの認知無効確認請求が権利濫用に当たるか(肯定)
「もっとも、日本の民法下で認知は現に父がある子を対象としてはすることができないと解されているのは、親子関係の公的な秩序として父が重複することは許されるべきではないとする趣旨から出たものであると解される。これを本件について見ると、もとより現在までにBがYの父として取り扱われたことがあったことをうかがわせる証拠ないし事情は見当たらないところ、日本の戸籍にはYがBの嫡出子であることをうかがわせる記載は見当たらず、また、ベトナムにおいてYの出生の登録がされたことをうかがわせる証拠ないし事情も見当たらないことからすれば、実際問題として、BがYの父として取り扱われる可能性は、今後とも乏しいというべきであって、本件胎児認知を有効なものとしたとしても、Yの父の重複が顕在化する事態が現実に生ずるとは直ちには想像し難いというべきである。」
このことに加えて、判決は、①XがYの生物学上の父であることを争うことを明らかにしているとはいい難いこと、②Xは、YをAがBとの婚姻期間中に懐胎した子であると認識しながら、本件胎児認知の届出をしたと推認されること、③本件胎児認知の届出が受理されたことについて、Y自身には何の落ち度もないこと、④X自身が、Yに対し、その父として接してきていたこと、⑤Yは、出生してから16歳になった現在に至るまで、ほぼ一貫して日本において日本人として生活してきたものであるところ、仮に本件胎児認知が無効であるとされた場合には、日本の国籍を喪失して(国籍法3条参照)、日常を一変させられることにもなりかねず、相応の精神的苦痛を受けるであろうことはもとより、社会生活の様々な場面においてそれまで予想だにしてこなかった不利益を被るなどの極めて過酷な状況に置かれることが想像されること、⑥XがYに対して本件胎児認知が無効であることの確認を求めるに至った動機は、CがX以外の男性との交際に及んだことに対する意趣返しにあったとも疑われることなどの事情を挙げ、本件の事実関係の下においては、本件胎児認知が無効であることの確認を求めるXの請求を許すことには、正義公平の観点から見て看過することのできない疑問が残るといわざるを得ないとして、Xの請求は、権利の濫用に当たり、許されないものであるというのが相当とした。
【コメント】
最三判平成26年1月14日民集68巻1号1頁は、認知者は、血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても、民法786条に規定する利害関係人として、自らした認知の無効を主張することができるとしつつも、「具体的な事案に応じてその必要がある場合には,権利濫用の法理などによりこの主張を制限することも可能である」としていた。本事例は、事例判断であるものの、実際に認知無効確認請求が権利濫用に当たると判断したものとして、注目に値する。