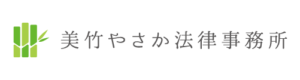A 養育費の支払を強制するためにはどのような方法がありますか?

B まず、現行法での取り扱いについて説明します。当事者が養育費の金額や支払期間等を合意できた場合には、合意の内容を(強制執行認諾文言付きの)公正証書、あるいは、家庭裁判所の調停調書にする必要がありました。
A 当事者が合意しただけでは、養育費の支払を強制できなかったのですね。当事者の合意がなければ強制できないのでしょうか?
B 家庭裁判所が養育費の支払を命じる審判し、これが確定した場合には、養育費の強制執行が可能になります。ただ、家庭裁判所に調停を申し立て、審判に移行し、これが確定するまでには、一定の期間がかかります。
A 養育費の支払を強制するのは大変なのですね。改正法では、この点はどのように変わったのでしょうか?
B 改正法では、父母が子の監護に関する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合であっても、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、民法及び法務省令によって定められる養育費の額の支払を請求できることになりました。これが法定養育費の制度です(改正法766条の3)。
A 法定養育費の制度では、金額はどのように定められるのですか?
B 法定養育費の金額は「父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額」とされています。この法務省令(※)は今後制定される予定です。
※ 法務省は、令和7年9月4日、法定養育費の金額を、請求をする父母の一方が離婚の時から引き続き監護を主として行う子1人当たりにつき月額2万円とすることなどを定める省令案を公示しました。パブリックコメントの受付期間は、同年9月4日から同年10月3日までとされています。

A 支払期間はどうなりますか?
B 始期は「離婚の日」であり、終期は、①父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日、②子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日、③子が成年に達した日のいずれか早い日とされています。
A 債務者は絶対に法定養育費を支払わないといけないのですか?
B いいえ、改正法では、債務者の支払能力等を考慮した調整がなされています。債務者が、「支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したとき」は、法定養育費の全部又は一部の支払を拒むことができます(改正法766条の3第1項ただし書)。
A 債務者の中には経済的に余裕があって、法定養育費以上の金額を、前記①~③の翌日以降も支払える人もいますよね。
B はい。ただ、当事者の収入状況に応じた養育費の支払を求める、あるいは子の大学卒業時までの支払を求めるためには、今後も当事者の協議や家庭裁判所の審判が必要です。
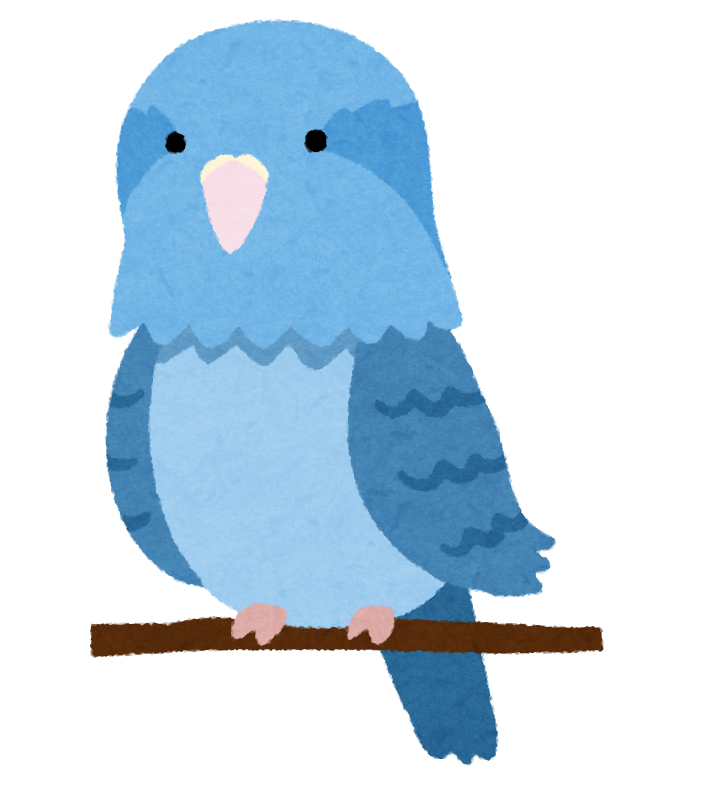
A 養育費の強制執行について、改正法で変わった点を教えてください。
B 改正法では、「子の監護に要する費用として相当な額」について一般先取特権を付与しました(改正法306条3号、308条の2)。
A 一般先取特権とは何ですか?

B 先取特権とは、債務者の財産について、他の債権者に優先して弁済を受けることができる担保権のことです。その中でも一般先取特権は、債務者の総財産を対象とするものであり、債務者の動産や不動産を対象とする先取特権よりも強い効力を与えられています。
A 養育費の債権者は、債務者の財産一般から優先的に回収できるということですか?
B 「子の監護に要する費用として相当な額」の範囲内では、そのとおりです。改正法により、子を監護する者は、義務者(債務者)の総財産に対し、他の債権者に優先して「子の監護の費用として相当な額」の弁済を受けられるようになりました。
A 一般先取特権が付与されると、強制執行しやすくなるのですか?
B 一般先取特権の実行(強制執行)においては、「一般先取特権の存在を証する文書」があれば足りるとされています。つまり、(強制執行認諾文言付き)公正証書や家庭裁判所の調停調書、確定審判書がなくても、父母が養育費の額等を合意した私的な文書さえあれば、強制執行の申立てができるようになりました。
A 法定養育費のときは、父母の合意文書はありませんよね。
B 法定養育費にも一般先取特権が付与されているため(改正法308条の2第3号)、父母の合意文書がない場合でも強制執行の申立てができます。ただし、その場合には、執行裁判所(地方裁判所)が必要があると認めるときは、債務者への審尋が必要になります。
A 他に強制執行手続の改正はありますか?
B 改正法では、養育費の民事執行手続のワンストップ化(財産開示手続・債務者の給与債権に係る情報取得手続・当該債権の差押えの手続の一体化)や、債務者の収入等に関する家庭裁判所の情報開示命令制度等が定められ、養育費がより実効的なものになりました。
A すべての子が養育費の支払を受けられるような運用が望まれますね。