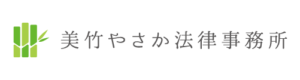B 今回は、いったん決まった親権者の変更や離婚後の監護について勉強しましょう。
A 離婚時に決まった親権者の変更ができるのですか?

B はい。離婚後の親権者については、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、子やその親族(民法725条に親族の定義があるけれども随分広いです)の請求で、親権者の変更(父母の単独親権から他の父母の単独親権に変更/単独親権から共同親権に変更/共同親権から単独親権に変更)をすることができるのですよ。たとえば、離婚前、父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、子にとって不利益となるおそれがあるため、この手続によって親権者の定めを是正することができます。
A 監護についても細かく決まったそうですね。
B 父母が離婚するときは、子の監護の分担について父母の協議で定められます。この定めをするに当たっては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないのは他の扱いと同じです。
監護の分担の例としては、次のような定めが考えられると思います。期限付きとするか否かはケースバイケースです。
【期間の分掌】「平日は父母の一方が子の監護を担当し、土日祝日は他方が監護を担当する」
期間の分掌は、定め方は簡単なようですが、祝日が日曜日に当たった時の代替休日や祝日に挟まれた平日は、祝日ではないけれど休日になる(国民の祝日に関する法律3条2項、3項)からこれを含めるかや、その間の養育費の清算や親子交流の内容なども決めておかないと紛争になるので注意する必要があります。また、期間の分掌に伴う強制執行が可能な子の引渡条項は適切でないという考えが強いです。
【事項の分掌】「子の教育に関する決定は同居親に委ねるが、その他の重要な事項については父母が話し合って決める」

A 共同親権と監護者の関係はどうなるのですか。
B 共同親権となった場合であっても、父母の協議で一方を「監護者」と定めることで、子の監護をその一方の親権者に委ねることができます。
この定めがされた場合には、「監護者」は、日常の行為に限らず、子の監護教育や居所・職業の決定を単独ですることができます。「監護者」でない親権者は、監護者が子の監護等をすることを妨害できないけれども、監護者による監護等を妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などに、子供の監護をすることができますよ。なお、今までは「面会交流」という言葉を使っていたけど、新法では「親子交流」という言葉に変わるようです。
子の監護について、監護者の定め、特定事項に係る親権者の指定、監護の分掌といった多くのメニューから選択できるようになったのはいいのだけれど、どのような場合にどのメニューを選択してどういう内容にすれば良いかがわかりにくくなったとも言えます。のちのちの紛争を防止するためには、弁護士に相談した方がいいかと思います。

A 私たち父母は、今回の民法改正施行前に離婚し、単独親権となっているのですが、改正法が施行されると自動的に共同親権に変更されるのですか?
B 改正法の施行によって自動的に共同親権に変更されることはありません。ただ、改正法の施行後、家庭裁判所が、子自身やその親族の申立てに基づいて、子の利益のための必要性を踏まえて、親権者を単独親権から共同親権に変更する場合がありますよ。
どのような場合に共同親権への変更が認められるかはケースバイケースですが、例えば、別居親が本来支払うべき養育費の支払を長期間にわたって合理的な理由なく怠っていたような場合には、共同親権への変更が認められにくいと言われています。また、子に対する虐待や夫婦間でのDVのおそれがあるときや、父母が共同して親権を行うことが困難であるときは、共同親権への変更は認められないようです。

A 婚姻届を出していない事実婚のときはどうなるのでしょう。父が認知した子がいる場合、父母双方が親権者になることはできますか?
B 改正法では、父が認知をした子は、母が単独親権者となります(民法819条4項)。
でも、父母の協議で、父母双方を親権者(共同親権者)あるいは父を親権者(単独親権者)とすることができるようになります(同項ただし書)。
父母の協議が調わないときは、家庭裁判所が、父母と子との関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮したうえで、子の利益の観点から、親権者を父母双方(共同親権)とするか、その一方とする(単独親権)かを定めることになります。
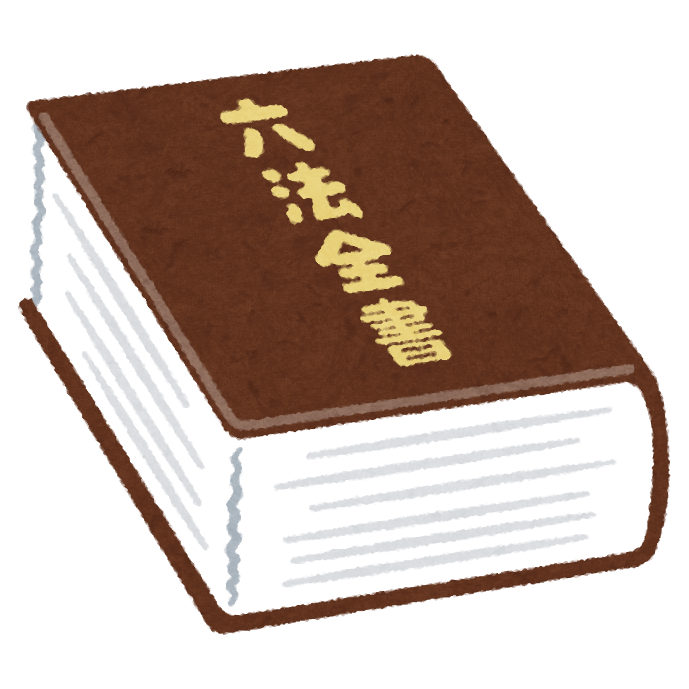
B あちこちで、「子の利益」という話が出てきたり、家庭裁判所が出てきたりで、簡単には説明できなくなっちゃいました。新法が施行されたら、もう少し分かりやすく説明できると思いますよ。
A 期待しています!
B 次回は、養育費について説明しますね。