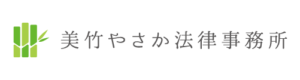共同相続人が被相続人の死亡後に預貯金を払い戻す行為が、民法906条の第2項の「共同相続人の一人又は数人により同行の財産が処分されたとき」に該当しないと判断された事例
[東京高決2024(令和6)年2月8日 家庭の法と裁判55号68頁]
[事実の概要]
(1)被相続人は、令和2年×月〇日に死亡した。
(2)被相続人の夫Aは、Aと被相続人との間の子ら(長女B・長男C・二男D)に対し、横浜家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てたが、不成立となり、審判に移行した。
(3)Aは、令和4年△月、遺言公正証書(亡A遺言書)を作成し、同遺言の遺言執行者としてDを指定した。
(4)Aは、同年死亡し、Dがその審判手続を受継した(家事事件手続法44条1項、3項)。
(5)Cは、Bが相続開始の直後に、被相続人名義の預貯金口座から引き出した現金を遺産の範囲に含めるべき旨を主張した。
(6)原審は、「(※Bは)引き出した現金を被相続人の医療費等の支払いに使用した旨主張し、審判時において遺産として存在すると認めるに足りる資料はなく、また、相続開始後の引出金について範囲に含めることについては相手方Bを除く相続人全員の合意もないから、審判時に遺産として存在するものとみなすこともできない(民法906条の2参照)。」旨の審判をした。
(7)Cは、原審判を不服として即時抗告した。
[決定の概要]
Cは、原審判が民法906条の2を適用したことは間違っており、①被相続人が入院後、その生前に払い戻された預貯金、②被相続人の死亡後に払い戻された預貯金、及び③死亡後に預貯金口座に入金された金員は全て、相続対象とすべきであると主張する。
まず、①及び③は、いずれも相続開始時に存在した「遺産に属する財産」(民法906条の2第1項)ではないから同条の適用はなく、また、これらを遺産分割審判の対象とする旨の共同相続人全員の合意もないから、遺産分割審判の対象となる遺産と認めることはできない。
②は、前記「遺産に属する財産」に該当する可能性があるところ、相手方らは、これを遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことに同意していないから、同条2項が適用されない限り、上記の払戻しに係る金員は遺産として存在するものとみなされないこととなる。
そこで、DやBが同条2項にいう「共同相続人の一人又は数人」に当たるか否かを検討する。
この点、一件記録によれば、Bはもとより、DもBに指示するなどして、被相続人の預貯金債権の全部又は一部を払い戻した疑いは払拭できないところである。
「もっとも、民法906条の2第2項の趣旨は、遺産に属する財産を処分した共同相続人が、同意をしないことにより不当な利得を得て、共同相続人間に不公平が生じるのを防止することにあるから、例えば、共同相続人の一人が、被相続人の生前、同人との間で、同人の死亡後における相続債務の支払等の事務処理に関して委任契約又は準委任契約を締結しており、これに基づいて、被相続人の死後に預貯金を払い戻して同事務処理の費用に充てた場合には、当該払戻行為は、同条2項の『共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたとき』には当たらないものと解するのが相当である。」
これを本件について見るに、被相続人が、生前、被相続人の所有する財産管理等に関する今後の全ての意思決定をDに一任する旨の誓約書に署名押印しており、被相続人とDとの間には、被相続人の死亡後の事務処理に係る委任契約又は準委任契約があったものと認定するのが相当であるから、仮にDが被相続人の預貯金債権の全部又は一部を払い戻したとしても、当該払戻行為は、同条2項の「共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたとき」には当たらないものと解される。
そうすると、本件において、Dに民法906条の2第2項が適用される余地はなく、Dの同意もない以上、被相続人の相続開始時に存在しその後払い戻された預貯金について、遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことはできない。
[ひとこと]
本決定は、民法906条の2第2項の趣旨に照らして同条項の適用の有無を判断したものであり、今後の実務の参考になると思われる。