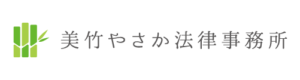未成年者が祖父母(監護親の父母)と養子縁組したことが養育費の額に影響を及ぼすべき事情の変更に該当するとして、調停条項中の養育費の支払の定めを取り消した事例
【東京高決2023(令5)年6月13日 家庭の法と裁判54号73頁】
〔事案の概要〕
本件は、元夫である抗告人(原審申立人)が、元妻である相手方(原審相手方)に対し、離婚の際の調停条項(以下「前件調停条項」という。)3項の、抗告人が相手方に対して当事者間の子である未成年者の養育費として月額15万円を支払うとの定めにつき、令和3年11月以降の支払を求める部分について取り消すことを求めた事案であり、上記未成年者が祖父母(監護親である相手方の父母)と養子縁組したこと(以下「本件養子縁組」という。)などが養育費の額に影響を及ぼすべき事情の変更に該当するか否かが争われた。
原審(千葉家審2022年9月29日)は、「一般的に、未成熟の子が養子縁組をした場合には養親が第一次的扶養義務者となり、実親は、養親が十分に扶養義務を履行できないときに限りその義務を負担すると言われているのは、権利者、すなわち、当該未成熟の子の親権者が再婚し、その再婚相手と養子縁組した場合を想定した解釈であり、また、第一次的扶養義務者が、いわゆる生産年齢(15歳以上64歳以下)であることなどを当然の前提としていると解すべきである。」と判示し、養親の年齢が高齢(満82歳と満78歳)であることなどから、本件養子縁組は養育費の額に影響を及ぼすべき事情の変更には該当しないなどとして、本件申立を却下した。
これを不服とする抗告人が即時抗告した。
〔本決定の概要〕
本決定は、「一般に、未成年者との養子縁組には、子の養育を全面的に引き受ける意思が含まれると解される上、未成年者養子制度の目的からいっても、未成年者に対する扶養義務は、第一次的には養親が負い、非親権者である実親は、養親が無資力その他の理由で十分に扶養義務を履行できないときに限り、次順位で扶養義務を負うものと解される。」と判示した上、養親となった祖父母が、25年以上にわたり不動産の委託管理、駐車場の経営等を目的とする同族会社の代表取締役又は取締役を務め、その本店及び養親宅の敷地である土地を共有していること、裁判所が、相手方に対し、祖父母の年収が分かる資料及び資産の全体を記載した陳述書等の資料の提出を求めたにもかかわらず、何らの資料も提出されなかったことなどからすると、養親である祖父母は、無資力その他の理由により十分に未成年者の扶養義務を履行することができないと認めることはできないとした。そして、本件養子縁組により、未成年者の実父である抗告人は第一次的な扶養義務者ではなくなったことが認められる上、第一次的な扶養義務者である養親が無資力その他の理由により十分に扶養義務を履行することができないときに当たるということもできないので、本件においては、養育費の支払を定めた前件調停条項3項の基礎とされた事情に変更が生じ、当初の調停合意の内容が実情に適合せず相当性を欠くに至ったというべきであるなどと判示し、原審を取り消して、抗告人が養育費を支払うと定めた前件調停条項3項につき、抗告人が本件審判に移行する前の調停を申し立てた令和3年11月以降の支払を定める部分を取り消した。