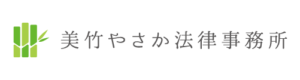審判で婚姻費用分担額が定まった後、分担額の減額を求めた事件の審判で、一時的な収入の増加とその後の減少を考慮し、差額を清算して分担額に反映させた例
〔事案の概要〕
抗告人(妻)が相手方(夫)に対し、婚姻費用分担請求をした事件において、令和2年3月13日、高裁は、相手方の総収入を約490万円、抗告人の収入をゼロと認定し、算定表に当てはめ、相手方に対し、未払金として121万円と、毎月11万円の支払いを命じた(審理終結日は令和2年2月28日 「前件決定」という)。相手方は、令和4年6月、婚姻費用分担(減額)の調停を申し立てたが不成立となり、審判に移行した。原審は、相手方には令和3年分の年金収入があり、職業費の割合を15%とし、収入約384万円と認定し、抗告人はゼロとし、算定表に当てはめ、調停申立時の令和4年6月からの分担額を月額7万円に減額した。これに対し即時抗告がなされたのが本件である。
〔東京高等裁判所2023(令5)年6月8日決定 家庭の法と裁判54号81頁〕
〔決定の概要〕
相手方は、前件決定の審理終結日である令和2年2月28日に、自営に係る会社から約806万円の振込送金を受け、これを取り崩して生活費や婚姻費用の支払に充ててきた。また、同年8月に持続化給付金100万円を受給し、同年分の営業所得を約971万円と申告している。これらの事実と資料から、相手方の令和2年の現実の総収入は約1228万円と認められる。これらの事情は、前件決定時にその前提とされていなかったというべきであるから、このような事情がある本件における減額変更の時期及び額は、令和2年分の総収入が増額し、令和3年分以降の総収入が減額したと見た場合の分担額の変更の時期や清算見込み額等をも勘案した上、公平の見地から定めるのが相当である。
具体的には、相手方の総収入を約1228万円、抗告人を0円として、算定表に当てはめ、令和2年3月から同年12月までは、分担額を月額24万円、令和3年1月以降は月額7万円とし、令和2年3月からの分担額である月額11万円との差額を清算すると、当審決定日(令和5年6月8日)時点で、令和2年3月から同年12月までの差額13万円の10カ月分130万円、令和3年1月から令和5年5月までは7万円と11万円との差額(マイナス4万円)の29か月分のマイナス116万円を合わせた14万円が未払い分として残る。以上の事情を勘案すると、公平の観点から、減額変更の時期及び額を、令和5年6月から同年12月まで月額9万円、令和6年1月から月額7万円とすることにより、両者の調整を図ることが相当である。