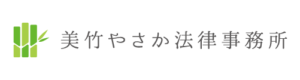遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないとされた事例
【最一小決令和5年10月26日 家庭の法と裁判52号75頁】
【事実の概要】
亡A(令和2年死亡)の相続人はAの子であるB及びY(相手方)の2名であったが、Aは、全財産をBに相続させる旨の遺言をしていた。そこで、YがBに対し、遺留分侵害額請求権を行使したところ、Bの妻であるX(申立人・抗告人)が、Yに対し、民法1050条に基づき、特別寄与料のうち相手方が負担すべき額として相当額の支払を求めた。
原々審(名古屋家裁判令和4年3月18日審判)は、Yは遺言により相続分を零とされたから、遺留分侵害額請求をしても特別寄与料は負担しないとしてXの申立を却下し、原審(名古屋高裁令和4年6月29日決定)も、同様に、相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料について、民法900条から902条までの規定により算定した相続分に応じた額を負担するから、遺言により相続分がないものと指定された相続人は特別寄与料を負担せず、このことは当該相続人が遺留分侵害額請求権を行使したとしても左右されないと判断して、Xの抗告を棄却した。そのため、Xが許可抗告の申立をし、原審が抗告を許可した。
【本決定の概要】
本決定は、「民法1050条5項は、相続人が数人ある場合における各相続人の特別寄与料の負担割合について、相続人間の公平に配慮しつつ、特別寄与料をめぐる紛争の複雑化、長期化を防止する観点から、相続人の構成、遺言の有無及びその内容により定まる明確な基準である法定相続分等によることとしたものと解される。このような同項の趣旨に照らせば、遺留分侵害額請求権の行使という同項が規定しない事情によって、上記負担割合が法定相続分等から修正されるものではないというべきである。」として、「遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと解するのが相当である。」と判示して、本件抗告を棄却した。
【ひとこと】
本決定は、遺留分侵害額請求権を行使した相続人が特別寄与料を負担するかという点に関する最高裁としての初めての判断を示したものであり、実務上も重要な意義を有するものといえる。