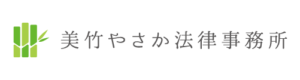直接及び間接の面会交流を拒否する未成年者の意向等に鑑み、親権者の承諾を得ることなく直接及び間接に面会交流をすることを禁止した例
〔事案の概要〕
申立人(母)と相手方(父)は、平成16年に別居し、未成年者(平成15年生)は、申立人同席のもと、月2,3回程度、相手方と面会交流を行っていた。申立人と相手方は、平成20年に親権者を申立人と定めて離婚したが、未成年者は別居中と同様の方法・頻度で相手方と面会交流を続けていた。その後、未成年者が高校1年生の頃、相手方と進学に関するやり取りをきっかけに令和2年2月以降、面会交流は実施されなくなった。令和2年5月、相手方は面会交流の調停を申し立てた(以下「前件調停事件」という。)。前件調停事件の家裁調査官による意向調査に対し、未成年者は「僕は父子二人で会う形について希望していません。」「僕が会いたいと思う時が来たら、僕の方から連絡します。」などと回答した。
相手方は、令和3年2月、前件調停事件を取り下げた。相手方は未成年者に対し「今まで毎月振り込んでいたお金を(未成年者に)直接会って手渡ししようと思います。」などと記載した手紙を送った。未成年者は「僕の気持ちは、変わりません。・・・いつか僕から連絡するまで、そっとしておいてください。」などと相手方にメールした。相手方は「直接受け取らないと、これからずっとお金を受け取れませんよ。先月から振込は止めました。」などと返信した。また、相手方は申立人宅を3回にわたり訪問し、チャイムを押すなどした。
申立人は、令和3年4月、面会交流禁止の審判の申立てをした。
〔名古屋家庭裁判所2021(令3)年9月3日審判 家庭の法と裁判55号102頁〕
〔決定の概要〕
相手方に会いたくないという未成年者の意思表示は強固なものであると認められる。この点、相手方は、未成年者の意思は母親である申立人に四六時中監視され、父親である相手方との会話に口を挟まれるという申立人の過干渉に置かれたことによるものであり、未成年者自らの独立した意思として尊重できるものではないと主張する。しかし、当時の未成年者の年齢(17歳)を考慮すると、未成年者による上記意思は、未成年者自身の真意であると認めるのが相当である。
そして、未成年者が相手方と会うことを拒否しているにもかかわらず、養育費の支払い名目で未成年者と会うことを強いるような相手方の行動は、未成年者を精神的に不安定にさせるものであり、未成年者の福祉に反するものであることは明らかである。
したがって、相手方に対し、未成年者との交流を直接及び間接を問わず、これを禁止することが相当である。