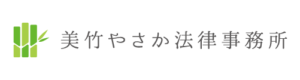A 面会交流(親子交流)については、どのような改正がありましたか。

B 改正前は、面会交流と呼ばれていましたが、改正法では、親子交流という言葉が使われていますので、以下では親子交流と言いますね。
改正法では、まず、親子交流の試行的実施について、規律が設けられました。
A 何のために、親子交流の試行的実施の規律が設けられたのでしょうか。
B 家庭裁判所は、調停・審判において、親子交流について定める際に、資料を収集して調査をしたり、父母間で調整をしたりします。このような調査や調整にあたっては、親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することが望ましい場合があります。そのため、改正法において、親子交流の試行的実施に関する規律が整備されました(人訴34条の4、家事事件手続法152条の3等)。
A 親子交流の試行的実施はどのような場合に認められるのですか。
B 家庭裁判所は、①子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、②事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができるものとされました(人訴34条の4、家事事件手続法152条の3)。

A 婚姻中別居場面における親子交流に関しても、今まで明文の規定がなかったそうですが、新たに規律が設けられたと聞いています。
B はい、父母が婚姻中に、子どもと別居している場合、これまではそのような場合の親子交流に関する規定がありませんでした。そこで、改正法は、婚姻中別居の場合の親子交流については、父母の協議によるが、協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定めることができるものとしました(民法817条の13等)。
A ほかには、親子交流に関して、どのような規律が設けられましたか。

B これまでは民法には、たとえば祖父母など父母以外の親族と子どもとの交流に関する規定はありませんでしたが、改正法は、父母以外の親族と子どもの交流について、規律を設けました。
A なぜ新しく規律を設けたのでしょうか。
B 父母以外の親族でも、子どもの利益の観点から交流を認めることが望ましい場合があるからです。そこで、改正法は、子どもの利益のために特に必要があるときは、家庭裁判所が父母以外の親族と子どもとの交流を実施するよう定めることができるとしました(民法766条の2)。
A 誰が父母以外の親族と子との交流の申し立てをするのでしょうか。
B 原則として父母ですが、例えば、父母の一方が死亡したり行方不明の場合など、ほかに適当な方法がないときは、①直系血族、②兄弟姉妹、③①②以外で過去に子どもを監護していた親族も、自ら、家庭裁判所に申立をすることができるようになりました。
ただし、父母以外の親族として申し立てができる場合は、その者と子との交流についての定めをするために他に適当な方法がないときに限るとされています(民法766条の2②)。