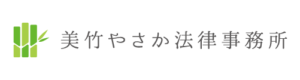2021.5.28
面会交流の具体的な頻度や時間について、未成年者の発言のみによって決することは相当でないとして、原審を変更して実施時間を延長し、かつ延長については段階的に行うとの方法を採用した事例
[名古屋高裁2021(令和3)年5月28日決定 家庭の法と裁判56号42頁]
[事実の概要]
妻と夫は別居し、その後妻は、未成年者とともに実家で両親と生活している。
夫は、別居後3か月間、概ね1か月に2回程度の頻度で、妻が同行した上で未成年者と面会交流をしていたが、妻あるいは妻の両親との間で面会交流の条件について意見の齟齬が生じた。そこで、夫は、名古屋家裁に、面会交流調停を申し立てた。
妻と夫は、調停期日において面会交流を暫定的に再開することに合意し、父と未成年者は、母の同行の下、約5か月ぶりに面会交流を行った。
その後、双方代理人間の協議により、概ね、①1か月に1回程度、②午前10時から午後3時までの5時間、③開始時刻及び終了時刻に妻宅前で引渡しを行う、④妻は面会交流に同行しない、との条件の下、暫定的に面会交流を実施した。
調査官作成の調査報告書によれば、未成年者は父との面会交流について「会えてよかった。全然変わってなくて安心した」、頻度について「今のままでいいかな」、「(面会交流が)楽しいからもっと遊びたいと思うこともあるけど」「(面会交流は)楽しいけど、土日はママとかおじいちゃんおばあちゃんと出かけるのも楽しい。同じくらい楽しい」等答えた。
原審は、令和2年9月8日、監護親である母親の負担や、未成年者の心情等を踏まえれば、「現在の条件の面会交流をすることが望ましい」として、
「1 相手方は、申立人に対し、次のとおり、申立人と未成年者を面会交流させなければならない。
(1)頻度 月1回程度
(2)各回の面会交流時間 午前10時から午後3時まで
(3)未成年者の受け渡し場所 相手方の自宅前
(4)相手方は、面会交流に同行しない。」
等と審判した。
父は、面会交流の1回当たりの実施時間を増やすべきとして、即時抗告した。
[決定の概要]
<主文>
1 原審判主文第1項(2)を次のとおり変更する。
各回の面会交流時間 午前10時から午後5時(ただし、令和3年6月以前に実施される面会交流にあっては午後3時、同年7月から同年9月までの間に実施される面会交流にあっては午後4時)まで
<理由>
「未成年者の年齢(上記面接当時8歳、現在9歳)等に照らせば、面会交流の具体的な頻度や時間について、未成年者の発言のみによって決することは相当でない」、「1回当たりの実施時間を、夜間にわたらない範囲で若干延長したとしても、それにより、未成年者が相手方や相手方の父母と外出等する機会が実質的に減少するとか、必要な家庭学習の時間を確保することが困難になるとは考えにくい」、「(別居後、概ね月2回程度の面会交流が実施されたこと)により具体的な弊害等が生じたことはうかがわれないこと、未成年者が上記のとおり抗告人との面会交流中にはもっと遊びたいと感じることもあることなども考慮すれば、上記のような時間延長が未成年者の福祉に反すると認めることはできない。また、未成年者の受け渡し場所がともに相手方の自宅前とされており、相手方は面会交流に同行しないことなども踏まえれば、上記のような時間延長により相手方の負担が大幅に増大するとも考えにくい。」
以上の諸点を踏まえれば、「頻度は維持しつつ、1回当たりの実施時間を午前10時から午後5時まで(7時間)に伸ばすのが相当である。ただ、未成年者が現時点では上記のような心情を示していることなどを踏まえれば、上記の実施時間については、本決定主文第1項のとおり、段階的に実現していくのが相当である。」
<ひとこと>
上記決定は、安易に未成年者の発言を根拠に暫定的な面会交流の条件を追認するのではなく、未成年者の年齢等を踏まえ、諸事情を多角的に考慮して条件を定めた点で、また段階的に時間を延長するという柔軟な方法を採用した点で、子の福祉に沿うものと評価できる。