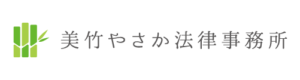【判決要旨】
親権者指定協議無効確認の訴えが, 人事訴訟法2条柱書きの「その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え」に当たるとして,人事訴訟として取り扱った上で, 原告の請求を認容した事例
【出典】
東京家裁令和4年10月20日判決
掲載誌 家庭の法と裁判 No.56/2025.6 49頁
事件名 親権者指定協議無効確認請求事件
裁判結果 認容 控訴棄却 上告棄却上告受理申立不受理で第一審判決確定
【事案の概要】
原告(妻)と被告(夫)は,4人の子(本判決口頭弁論終結時いずれも未成年)をもうけた夫婦であったところ,戸籍上は,子らの親権者をいずれも被告と定めてたと記載のある協議離婚届けをもとに協議離婚したものとされている。
これに対して,原告は,原告の不貞行為を知った被告から白紙の状態の離婚届の用紙を示され, 言われるがままにこれに署名押印をしたにすぎず,子らの親権者をいずれも被告と定める協議をしたことはない旨を主張し,被告に対して親権者指定協議が無効であることの確認請求訴訟を東京家庭裁判所に提起した。
なお,離婚が有効であることについて当事者間に争いはなく、訴訟の対象にはなっていない。
【本判決理由 親権者指定協議無効確認の訴えは人事訴訟といえるか】
(1)本判決は,「本件のような親権者指定協議無効確認の訴えは,人事訴訟について定める人事訴訟法2条各号所定の訴えのいずれにも該当するものではないが,同条柱書きの 「その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え」に当たるものとして取り扱うのが相当である。」と判示して家裁が扱うことのできる「人事に関する訴え」と解した。
(2)その上で,本判決は,本件の事実関係として,原告と被告との間で子らの親権者をいずれも被告と定めることの合意がされていたとか,原告が子ら の親権者をいずれも被告と定めることを認識認容していたなどというには, 説明の付かないところが多く見られるとして,原告と被告との間で子らの親権者をいずれも被告と定める協議がされていたとは認められとして,原告の請求を認容した。
【解説】
この訴訟の法律上の問題点は2点ある。
①この訴えにつき、家庭裁判所で審理できるか、できるとして訴訟か審判か(親権者指定協議の無効を前提として新たな親権者を定める審判申立てになろうか)という問題がある。
東京家裁家事第6部は、2023年出版の書籍で従前の扱いを変更し、親権者指定協議無効確認の訴えが人事訴訟法2条柱書きの「その他の身分関係の形成 又は存否の確認を目的とする訴え」 に当たるとし、この解釈は現在では同部において定着したものとなっているようである。
②また、現行民法819条1項は「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」とあるので、離婚協議が無効になった場合は、協議離婚の要件が欠け、離婚そのものの有効性に影響を及ぼさないかという疑問があるが、親権者指定は、協議離婚届出受理の形式要件でしかなく、離婚自体の効力には影響がないと解されており、裁判例上も異論がない。
なお、改正予定の民法765条2号は、協議離婚届出時点で親権者指定家事審判又は家事調停の申立てがされている場合は、届出には親権者指定の協議は不要としている。