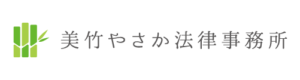遺産分割協議書が証拠として提出されていない場合でも有効に遺産分割協議が成立していたと認められた事例
【神戸地尼崎支判令和4年6月6日 家庭の法と裁判55号97頁】
【事実の概要】
原告Xは、母である亡A(平成31年死亡)とその前夫との間の子である。亡Aの夫である亡B(平成5年死亡)は、亡Aとの間には子供がいなかったが、前妻との間に、亡C(令和元年死亡)、D、E、F(昭和59年死亡)の4人の子供がいた。被告Yは亡Cの子供であった。亡Bの法定相続人は、亡A、C、D及びEであったが、平成6年3月20日の遺産分割協議書(以下、「本件協議書」という。)には、亡B名義の特別口座に記録された振替株式(以下、「本件株式」という。)について失念していたため、記載がなかった。Xは、遅くとも平成6年6月20日までに本件株式を亡Aが取得する旨の再度の遺産分割協議が成立したと主張し(主位的主張)、また、仮に遺産分割協議が成立していなかったとしても、亡Aが時効取得したから、Xがこれを相続により取得した旨主張し、Yに対して、本件株式につき、X名義の預金口座を振替先口座とする振替手続の申請をするよう求めて提訴した。これに対し、Yは再度の遺産分割協議を否認し、取得時効の成立も争った。
【本判決の概要】
本判決は、①本件株式を亡Aが取得したことによる相続税修正申告書(以下「本件修正申告書」という。)が提出されていること、②D及びEは、令和2年3月にX代理人からの照会に対し、亡Bの相続人全員の遺産分割協議により、亡Aが本件株式を単独取得したことを認める旨の回答書を作成していたこと、③本件協議書及び本件修正前申告書において、相続人間で唯一遠方に居住し、有限会社Sの経営に関与していない亡Cが兄弟間で最も高額な預金を取得する一方、有価証券及び不動産を取得せず、D及びEが有限会社Sの出資のうち500口及び預金等を取得し、亡Bがその余の有価証券等を取得することとなっていたことからすると、後に判明した本件株式について、亡Aのみが取得するとの遺産分割協議を改めて行うことは、ごく自然な流れというべきであること、④証拠提出されている本件修正申告書には亡A及び亡Cの印影の表示がない状態であり、本件修正申告書の内容と整合する遺産分割協議書の証拠提出がない以上、当時の税務署において、相続税の修正申告に当たって、全相続人による申告書への押印、その裏付けとなる遺産分割協議書の提出が必要とされたかどうかは証拠上判然としないことを考慮しても、亡A、D、亡C及びEは、平成6年3月20日より後に、本件株式を亡Aが取得したとの遺産分割協議を行い、これに基づき、亡Aが本件株式を取得したと認めるのが相当であると判示し、Yに対して本件株式のX名義の口座を振替先口座とする振替手続の申請を命じた。
【ひとこと】
遺産分割協議書がなくても遺産分割協議の成立を認めた事例として参考となる。